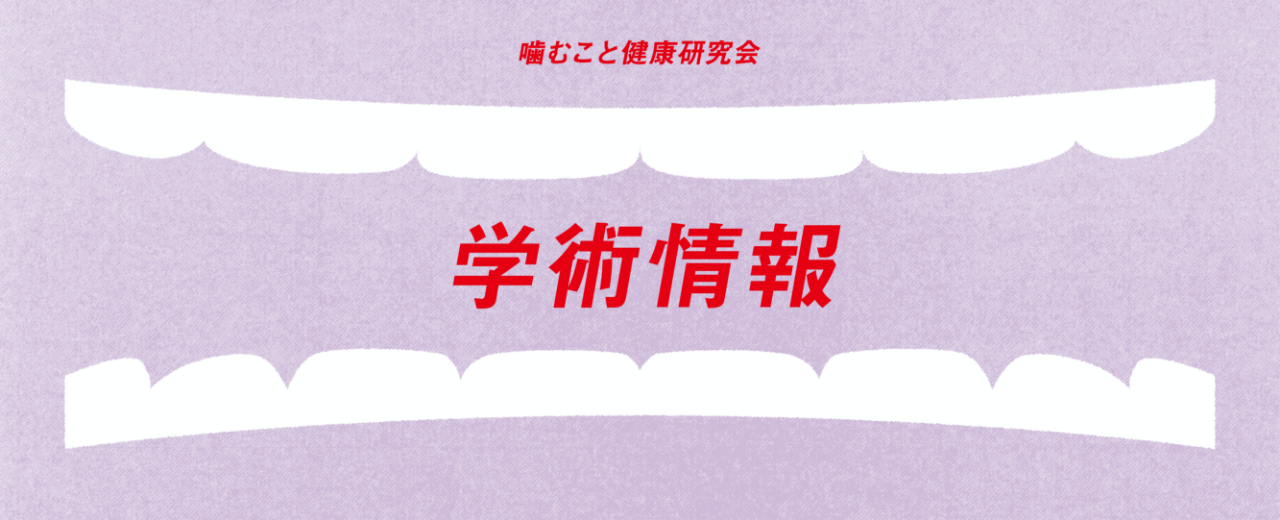学術情報
噛むことに関する学術情報(ヒト試験結果)をご紹介します。
2024年
-
Oral Frailty and Its Relationship with Physical Frailty in Older Adults: A Longitudinal Study Using the Oral Frailty Five-Item Checklist(高齢者におけるオーラルフレイルと身体的フレイルの関係:OF-5チェックリストを用いた縦断研究)
Hiroshi Kusunoki et al. Nutrients. 17(1): 17 (2024)
要約:兵庫県篠山・丹波地域のフレイルと診断された65歳以上の高齢者におけるオーラルフレイルと身体的フレイルの関係、および予後をOF-5を用いて評価した。オーラルフレイルは筋肉量、歩行速度、身体機能の低下と相関関係にあることが示され、初期のOF-5スコアが高い人は2-3年後の身体的フレイルの増加を予測できることが明らかとなった。OF-5によるオーラルフレイルの早期発見が、高齢者の全体的なフレイルの進行を防ぐのに役立つ可能性がある。
-
Effect of chewing hard material on boosting brain antioxidant levels and enhancing cognitive function(硬いものを噛むことによる脳の抗酸化レベル向上と認知機能強化への効果)
Seungho Kim et al. Front Syst Neurosci. 18: 1489919 (2024)
要約:健康な若年成人(52名の大学生)を対象に、咀嚼後の脳内グルタチオン(GSH)濃度の変化と認知機能との関連をガム咀嚼とガムより硬いウッドブロック咀嚼で検討した。その結果、ウッドブロック咀嚼群は脳内GSH濃度を有意に上昇させ、かつGSH濃度と記憶数値が正の相関が認められた。適度に硬いものを噛むと、GSHなどの脳の抗酸化物質濃度が上昇し、認知機能に影響を及ぼす可能性がある。
-
Effect of Cognitive Decline on Mandibular Movement during Mastication in Nursing Home Residents(老人ホーム入居者における咀嚼時の下顎の動きと認知機能低下への影響)
Enri Nakayama et al. J Clin Med. 13(20): 6040 (2024).
要約:老人ホーム入居者を対象に(介入群8名、対照群8名)1カ月のガム咀嚼トレーニング1日3回、毎食前10分間(左右各5分ずつ)30日行い、介入前後で食いしばりによる咬筋の酸素動態およびVASによる咬筋疲労を測定した。その結果、ガム咀嚼群は食いしばり時咬筋の総ヘモグロビンおよび酸素化ヘモグロビンの有意な増加、1/2回復時間の短縮が認められた。加えて咬筋疲労の減少傾向を示した。
-
The Association of Walking Ability with Oral Function and Masticatory Behaviors in Community-Dwelling Older People: A Cross-Sectional Study(地域在住高齢者の歩行能力と口腔機能および咀嚼行動との関連性:横断的研究)
Takako Ujihashi et al. Geriatrics (Basel). 9(5): 131 (2024).
要約:高齢者の咀嚼行動、口腔機能、歩行能力(タイムドアップアンドゴーテスト (TUG) により評価)との関連について、地域在住高齢者100名に対する調査研究を行った。TUG時間と舌圧、および舌口唇運動機能(/ta/および/ka/)の間に中程度の負の相関が見られた。さらに、TUG時間と咀嚼速度、および食事時間の間にも中程度の負の相関が見られた。地域在住の高齢者において、咀嚼速度、舌の強さ・機能の低下が歩行能力の低下と関連していることが示唆された。
-
Association of physical function with masticatory ability and masticatory habits: a cohort study(身体機能と咀嚼能力および咀嚼習慣との関連:コホート研究)
Moeno Takeshita et al. BMC Oral Health. 24(1): 1277 (2024).
要約:身体機能と咀嚼能力、咀嚼習慣との関連性について調べるため65~84歳の地域在住高齢者146名に対する1年間の追跡調査を行った。客観的咀嚼能力と主観的咀嚼能力の間には関連が認められたが、客観的咀嚼能力と咀嚼習慣の間には関連は認められなかった。主観的咀嚼能力と咀嚼習慣は1年後の身体機能に影響を及ぼしているようであった。高齢者の身体機能を維持するためには、咀嚼能力だけでなく咀嚼習慣も考慮した早期介入が必要である。
-
Effects of Different Gum Hardness on Masseter Muscle Activity During Gum Chewing: An NIRS Oximetry Study(ガムの硬さの違いがガムを噛んでいるときの咬筋の活動に与える影響:NIRS酸素飽和度測定による研究)
Takahiro Sakaue et al. Adv Exp Med Biol. 1463: 341-345 (2024).
要約:ガムの硬さの違いが咬筋組織の酸素動態と筋活動に与える影響を調べた。硬さの異なる3種類のガムを使用して、酸素動態、筋活動、心拍数の測定、視覚的アナログスケールによる咬筋疲労の程度を評価した。ガムの硬度が増すにつれて、酸素飽和度の大幅な低下とデオキシヘモグロビン濃度の大幅な増加が観察された。同様に、筋肉活動、心拍数、および筋肉疲労もガムの硬度が増すにつれて大幅に増加した。噛む運動を伴う口腔治療においてガムを選択するときは、適切な硬さのガムを選ぶことが重要である。
-
Effect of Gum Chewing Training on Masseter Muscle Oxygen Dynamics(ガム咀嚼トレーニングが咬筋酸素動態に与える影響)
Arata Tsutsui et al. Adv Exp Med Biol. 1463: 329-334 (2024).
要約:ガム咀嚼 (GCh) トレーニングが咬筋酸素動態に及ぼす影響を調べた。GChトレーニングは、1日3回、毎食前に10分、30日間行われ、介入前後でクレンチングの影響を評価した。トレーニング後、クレンチング中の総ヘモグロビンと酸素化ヘモグロビンの有意な増加が観察され、1/2回復時間が有意に短縮された。筋疲労のVASスコアは、トレーニング後に減少傾向を示した。1 か月の GCh トレーニングにより、噛みしめと回復中の咬筋の酸素動態が変化し、筋肉の有酸素能力が向上した。
-
Effects of Dual Tasks Including Gum Chewing on Prefrontal Cortex Activity(ガム咀嚼を含む二重課題が前頭前野の活動に与える影響)
Arata Tsutsui et al. Adv Exp Med Biol. 1463: 153-158 (2024).
要約:歩行、ガム咀嚼(GCh)、歩行とガム咀嚼の同時二重課題(歩行+GCh)を行いながら心地よい音(PS)を聴くことによる前頭前野(PFC)活動への影響を調べた。コントロール条件は、PSを聴きながらの休憩(運動なし)とした。コントロールと比較して、GChおよび 歩行+GCh タスク中にPFCの活動が有意に高まった。また、GChおよび 歩行+GCh は、VAS測定(快適さの自己評価)において有意に高い値を示した。GCh または 歩行+GCh中にPSを聴くと、中枢下部領域におけるPFCの活動が高まり、肯定的な感情の変化が誘発されると考えられる。
-
Consensus statement on "Oral frailty" from the Japan Geriatrics Society, the Japanese Society of Gerodontology, and the Japanese Association on Sarcopenia and Frailty(日本老年医学会、日本老年歯科学会、日本サルコペニア・フレイル学会による「口腔フレイル」に関する合意声明)
Tomoki Tanaka et al. Geriatr Gerontol Int. 24(11): 1111-1119 (2024).
要約:オーラルフレイルは、口腔機能が健全と低下の中間の状態であり、その評価方法として、歯科保健専門家を必要としないオーラルフレイル5項目チェックリスト(OF-5)が提案されている。(i) 歯が少ない、(ii) 咀嚼が困難、(iii) 嚥下が困難、(iv) 口が渇く、(v) 発音口腔運動能力が低い、このうち少なくとも 2 つに該当する場合オーラルフレイルと定義される。OF-5の開発は、一般の人々のオーラルフレイルに関する関心を高め、医科と歯科の医療従事者の連携を促進することを目的としている。
-
Association between self-reported difficulty in chewing or swallowing and frailty in older adults: A retrospective cohort study(高齢者の咀嚼や嚥下の困難と虚弱性の自己申告との関連性:後ろ向きコホート研究)
So Sato et al. Geroscience. Aug 30 (2024).
要約:本コホート研究では、359,111人の75歳以上の高齢者に対して、咀嚼または嚥下の困難さ、誤嚥性肺炎による入院、全原因入院、1年以内の全原因死亡率などの結果との関連を評価した。39.0%の高齢者が自己申告により口腔機能の障害を報告した。咀嚼困難は、誤嚥性肺炎による入院、全原因入院、全原因死亡率のリスクと有意に関連していた。咀嚼困難と嚥下困難は相乗効果を示し、全原因死亡リスクを有意に増加させた。
-
Increased Waist Circumference after One-Year Is Associated with Poor Chewing Status(1年後のウエスト周囲径の増加は咀嚼状態の悪さと関連している)
Riku Yamazaki et al. Healthcare (Basel). 12(13): 1341 (2024).
要約:日本人成人8,068名において1年後のウエスト周囲径(WC)の増加が5cm以上の場合を不健康な増加と定義し、合計で613人 (7.5%) がこの基準を満たしていた。また、ベースラインでの自己申告式質問票により1080人 (13%) が咀嚼状態が悪いと判断された。WCの5cm以上の増加は、性別、WC、BMI (ボディマス指数)、咀嚼状態と正の相関があることが判明した。これらの結果は、日本人成人の1年後のWCの増加は、咀嚼状態の悪さと関連していることを示唆している。
-
Efficacy of hard gummy candy chewing in improving masticatory function in Japanese children aged 6-12 years: A clinical trial(ハードグミキャンディの咀嚼による6~12歳の日本人児童の咀嚼機能改善効果:臨床試験)
Yohei Hama et al. J Oral Biosci. 66(3): 525-529 (2024).
要約:ハードグミキャンディを噛むことが6〜12歳の日本の子供の咀嚼機能に与える影響を調べた。4週間、1日2回、ハードグミキャンディを噛むことにより、口唇閉鎖力および右咬合力は有意に増加し、その効果は訓練終了後さらに4週間持続した。咀嚼能力も訓練後に改善したが、その効果は持続せず、訓練終了後4週間で低下した。
-
Relationships between oral function, dietary intake and nutritional status in older adults aged 75 years and above: a cross-sectional study(75歳以上の高齢者における口腔機能、食事摂取量、栄養状態の関係:横断的研究)
Xiaoqing Wu et al. BMC Public Health. 24(1): 1465 (2024).
要約:中国の高齢者(75歳以上)の口腔機能・栄養状態と食事摂取量との関係について横断研究により調査を行った。簡易栄養状況評価表(MNA-SF)スコアに基づいて、栄養状態良好群と栄養不良群に分けた結果、参加者の40.6%が栄養不良群であった。75歳以上の高齢者では栄養不良の割合が高く、運動頻度、脳卒中、咀嚼・嚥下機能、野菜・果物摂取量と有意に相関していた。これらの結果より、高齢者の栄養管理においては、口腔機能と食事摂取量を理解したうえで指導を行うことが重要である。
-
The effectiveness of a self-reported questionnaire on masticatory function in health examinations(健康診断における咀嚼機能に関する自己申告質問票の有効性)
Kazunori Anzai et al. Odontology. 112(4): 1361-1369 (2024).
要約:咀嚼機能質問票が歯と口腔の状態を反映し、全身の健康および口腔の健康の改善に役立つかどうかを、2年連続で国民健康保険指定の健康診断を受けた合計6599人を対象として調べた。いくつかの検査項目について、質問票の回答と歯科検診結果の間に有意な関係があった。健康診断後の全体的な歯科受診率は42.3%であり、咀嚼機能に何らかの問題があった人では、歯周病の改善、血圧の改善が見られた。本研究の結果より、咀嚼機能に関する質問票は歯と口腔の健康状態を反映しており、さらにメタボリックシンドロームの改善に潜在的に関連していることが示唆された。
-
Effect of gum-chewing exercise on maintaining and improving oral function in older adults: A pilot randomized controlled trial(ガムを噛む運動が高齢者の口腔機能の維持と改善に及ぼす影響:パイロットランダム化比較試験)
Kenta Kashiwazaki et al. J Dent Sci. 19(2): 1021-1027 (2024).
要約:高齢者の口腔機能に対するガムを噛む運動の効果を調べた。介入群には実験用ガムの咀嚼、対照群には実験用タブレットの摂取を1か月間継続させた後、口腔機能評価を行った。介入群の舌圧は対照群よりも有意に高かった(P=0.027)。グループ内比較では、最大咬合力、非刺激唾液流量、舌と口唇の機能、咀嚼チェックガムのカラースケール値が介入群で有意に増加した。ガムを噛む運動が高齢者の口腔機能を改善できる可能性が示唆された。
-
Accuracy of newly developed color determination application for masticatory performance: Evaluating color-changeable chewing gum(咀嚼能力を評価するための新開発の色判定アプリケーションの精度:色が変わるチューインガムの評価)
Yohei Hama et al. J Prosthodont Res. 68(4): 650-657 (2024).
要約:咀嚼により色が変わるチューインガム(ロッテ製)の色判定を行うためのスマートフォン用アプリケーションを開発し、20歳から39歳の健康な被験者100名によるフィールド検証を実施した。2回の繰り返しショットのクラス内相関係数は0.97以上の高い値を示し、比色計による評価値との比較においても有意で強い相関(相関係数0.92以上)が確認された。このスマートフォン用アプリケーションを使用することにより、咀嚼後の色変わりチューインガムの評価値を簡単、迅速、正確に測定することが可能となった。
-
Effect of vegetable consumption with chewing on postprandial glucose metabolism in healthy young men: a randomised controlled study(健康な若い男性における野菜の噛みながらの摂取が食後グルコース代謝に与える影響:ランダム化比較試験)
Kayoko Kamemoto et al. Sci Rep. 14(1): 7557 (2024).
要約:野菜を固形で摂取した場合とピューレで摂取した場合の食後血糖代謝への影響を調べた。千切りキャベツ摂取群、ピューレ状キャベツを摂取群それぞれに対し、エネルギーゼリー摂取後の血液サンプルを経時的に採取した。群間で血漿グルコース濃度に差はなかったものの、血漿インスリンおよびグルコース依存性インスリン分泌ペプチド (GIP) 曲線下面積の増分値は、咀嚼群の方が大きかった。また、食後総グルカゴン様ペプチド-1 (GLP-1) 濃度は、45、60、90分時点で咀嚼群の方が高かった。この研究により、キャベツを咀嚼しながら摂取すると食後インクレチン分泌が促進されるが、食後グルコース濃度には影響を与えないことが示された。
-
The predictive value of masticatory function for adverse health outcomes in older adults: a systematic review(高齢者の健康障害に対する咀嚼機能の予測値:系統的レビュー)
Menke J de Smit et al. J Nutr Health Aging. 28(5): 100210 (2024).
要約:咀嚼機能はさまざまな健康事象と関連している。システマティックレビューにより、高齢者の虚弱性、サルコペニア、栄養失調などの有害な健康事象と咀嚼機能との関連を抽出した。咀嚼機能は、最大咬合力(MOF)が最も頻繁に評価されていた。特定された健康アウトカムは、身体パラメータとサルコペニア、転倒歴、栄養状態、虚弱性、認知機能および死亡率の6つのカテゴリーに分類された。すべての前向き研究で、高齢者の咀嚼機能の低下が有害な健康アウトカムと関連していることから、適切な口腔ケアによって咀嚼機能の低下を防ぐことは、健康的な老化に寄与する可能性がある。
-
The use of color-changeable chewing gum in evaluating food masticability(食品の咀嚼性を評価するための色が変わるチューインガムの使用)
Toshihiro Yashiro et al. Eur Geriatr Med. 15(2): 497-504 (2024).
要約:65歳以上 (平均82.6歳) の患者50名 (男性 48%) に対して、色変わりチューインガム(ロッテ製)により、3つのグループ (肉が咀嚼可能、柔らかいおかずが咀嚼可能、咀嚼能力不十分) に対して咀嚼力の評価を行った。理学療法士と栄養士の2 人の評価者がカラースケールで判定し、3つのグループ間のカッパ係数により評価を行った。分類一致のカッパ係数は、理学療法士と栄養士でそれぞれ 0.908 と 0.909 であった。カラースケールに関する2人の評価者間の一致は、カッパ係数で0.938であった。色変わりチューインガムは、高齢者施設や高齢者家庭での咀嚼力チェックに有用である。
-
Relationship between a gum-chewing routine and oral, physical, and cognitive functions of community-dwelling older adults: A Kashiwa cohort study(ガムを噛む習慣と地域在住高齢者の口腔機能、身体機能、認知機能との関係:柏コホート研究)
Jun Kawamura et al. Geriatr Gerontol Int. 24(1): 68-74 (2024).
要約:地域在住の高齢者1474名(平均年齢76.1±5.8歳、女性45%)のガムを噛む習慣と口腔機能、身体機能、認知機能、食事摂取量、ライフスタイルとの関係を調べた。解析の結果、14%が毎週30分以上ガムを噛む習慣があった。ガムを噛む習慣のある高齢者では口腔機能が有意に高く、口腔虚弱者は大幅に少なかった(調整オッズ比0.581、95%信頼区間0.340-0.993)。さらに、ガムを噛む習慣のあるグループでは、握力を含む身体機能、認知機能が有意に高かった。これらの結果は、ガムを噛む習慣が口腔機能の維持と虚弱の予防に寄与する可能性があることを示している。
-
Chewing difficulties mediated association between edentulism and depressive symptoms among middle aged and older population(中高年層では咀嚼障害が無歯症とうつ症状の関連を媒介している)
Xing Qu et al. J Oral Rehabil. 51(3): 556-565 (2024).
要約:無歯顎症809人と無歯顎症でない2,628人に対して、疫学研究センターうつ病尺度 (CES-D-10) を用いて解析を行った。その結果、無歯顎症ほどうつ病の発生率が高くなることが示された (OR:1.39、95%CI:1.19-1.63)。咀嚼障害が無歯顎症とうつ病の関連に及ぼす平均媒介効果は0.010 (95%CI:0.005-0.015)、平均直接効果は0.072 (95% CI:0.036-0.11) であった。咀嚼障害の媒介割合は11.7% (95%CI:0.079-0.21) であった。高齢者層の精神的健康を改善するには、基本的な口腔機能を無視すべきではない。
-
Differences in oral hypofunction prevalence and category measures across age groups and sex in Japan: a pilot study(日本における口腔機能低下の有病率とカテゴリー指標の年齢層と性別による違い:パイロットスタディ)
Rena Hidaka et al. BMC Oral Health. 24 (1): 1483 (2024).
要約:155 人の健康な成人を若年 (20-39歳)、中年 (40-64 歳)、高齢 (65歳以上) のグループに分け、口腔機能と身体機能に関する線形回帰分析を行った。高齢群では、若年群や中年群よりも 口腔機能低下 (OHF) の有病率が有意に高かった。OHF の指標である口腔衛生、最大舌圧 (MTP)、口唇舌運動機能 (LTMF)、最大咬合力も高齢群で有意に低かった。口腔衛生と LTMF の指標は年齢と中程度の相関を示した。握力は、男性と女性の両方の参加者において、MTPおよびLTMFと有意に関連していた。
-
Unfavourable Outcomes in Older Adults with Oral Frailty: A Scoping Review(口腔虚弱高齢者の予後不良:スコープレビュー)
Sheng-Rui Zhu et al. Clin Interv Aging. Nov 28: 19: 1979-1995 (2024).
要約:このレビューは 28 件の論文で構成されており、そのうち 20 件は横断研究、8 件は前向きコホート研究であった。20の口腔虚弱 (OF) 評価ツールが存在し、OF の評価に最も頻繁に使用された方法は、Tanaka らの方法と Oral Frailty Index-8 (OF-8) であった。高齢者の OF に関連して発生する好ましくない結果としては、身体的な虚弱、栄養失調、食事の多様性の低さ、社会からの引きこもり、障害、および歩行速度の低下であった。
-
Association of oral frailty with medical expenditure in older Japanese adults: The study of late-stage older adults in Tottori (START Tottori)(日本の高齢者における口腔虚弱性と医療費の関連性:鳥取県の後期高齢者を対象とした研究(START鳥取))
Eri Arai et al. Gerodontology. Jun 17 (2024).
要約:鳥取県に居住している後期高齢者2190人(男性860人、女性1330人、75~94歳)を対象として、健康、口腔虚弱前、口腔虚弱の3グループに分類し、医療費と歯科費用、診察日数、合併症との関連を調べた。口腔の虚弱性と外来診療にかかる医療および歯科診療の年間費用の高さとの間には、有意な関連が認められた。口腔の脆弱さは、口腔衛生問題以外の疾患の発生と重症度と関連している可能性が示唆された。
-
Oral frailty is associated with mortality independently of physical and psychological frailty among older adults(口腔の虚弱性は、高齢者の身体的・心理的虚弱性とは関係なく死亡率と関連している)
Daiki Watanabe et al. Exp Gerontol. Jun 15: 191: 112446 (2024).
要約:京都・亀岡研究をベースに65歳以上の成人11,374人に対して、口腔虚弱指数-8に従って、堅牢、口腔プレ虚弱、口腔虚弱、口腔重度虚弱の4つのカテゴリーに分類した。追跡期間中央値5.3年(57,157人年)の間に、1184人の死亡が記録された。口腔プレ虚弱性(HR:1.29、95%CI:1.02-1.63)、口腔虚弱性(HR:1.22、95%CI:1.01-1.48)、および口腔重度虚弱性(HR:1.43、95%CI:1.16-1.76)は、死亡率のHRの高さと関連していた(p=0.002)。
-
Impact of Masticatory Performance and the Tongue-Lip Motor Function on Incident Adverse Health Events in Patients with Metabolic Disease(代謝性疾患患者における咀嚼能力と舌・唇運動機能が健康被害の発生に及ぼす影響)
Mitsuyoshi Takahara et al. J Atheroscler Thromb. 31(12): 1664-1679 (2024).
要約:代謝性疾患の患者1,000名に対して、一般化傾向スコア (GPS) 法により、咀嚼能力と有害健康イベント (全死因死亡、心血管疾患、骨折、悪性腫瘍、肺炎、認知症の複合) の発生率との関連性を調べた。中央値36.6か月の追跡期間中に、191 人の患者で有害な健康イベントが観察され、GPS 調整用量反応関数において、咀嚼能力が有害な健康イベントの発生率と逆相関していることが示された。3年間の発生率は、下位四分位で 22.8%、上位四分位で 13.6%であった (P<0.001)。また、舌唇運動機能との相関においても同様な傾向がみられた。
-
プロアスリ-トにおけるガム長期摂取による口腔, 身体的パフォ-マンスへの影響 ―オ-プンラベル非ランダム化前後比較試験―
松井美咲ら. 薬理と治療. 52(10): 1219-1224 (2024).
要約:ガムの継続的摂取がスポーツ選手の口腔および身体能力に及ぼす影響を調べるため、22名のプロサッカー選手が、非無作為化事前事後比較試験に参加した。被験者は、1年間のガム摂取を行い、介入前後で口腔パフォーマンスと身体パフォーマンスを測定した。その結果、咬合バランス、静的バランス、垂直跳びが介入後に有意に改善された。1年間のガム摂取は、咬合バランスと身体能力を改善する可能性が示唆された。
https://www.pieronline.jp/content/article/0386-3603/52100/1219
-
ガム咀嚼による顔表面の筋活動への影響 : オープンランダム化クロスオーバー比較試験
松井美咲ら. アンチ・エイジング医学(日本抗加齢医学会雑誌). 20 (3): 198-203 (2024).
要約:2粒あるいは4粒のガム咀嚼中の筋活動状態を測定した結果、3分間のガム咀嚼中の筋電図計測において、無摂取時と比較して咬筋、眼輪筋、口輪筋、顎二腹筋相当部において有意な筋活動増加が認められた。顔表面温度では、頬、正面、口辺においてガム咀嚼後で有意な上昇が認められた。ガムの粒数による筋活動の有意な変化はみられなかった。